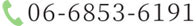よくあるご質問
Q1. お葬式の日程は、どうやって決まるのですか?
A.
お葬式が、主に自宅で行われていた時代では亡くなられた日がお通夜、翌日に葬儀告別式といった流れが一般的でした。遺族にとっては、まさにあっという間の二日間といった感じで過ごすことになったのでしょう。
最近では、火葬場の空事情から止む無く日延べをしてからのお通夜ということが多くなってまいりました。
日程を決める際に最も重要なのは、宗教者の都合になります。次に火葬場、式場とご希望やお集まりいただく方々への配慮をもって、決定することになります。
ご遺族に変わり葬儀社がすべてを調整いたしますので、ご心配やご希望を明確にお伝えいただくことが必要です。
Q2. 葬祭ディレクターとはなんですか?
A.
ご葬儀のご相談から、プランの作成、進行のサポート等一切を担当いたします。
厚生労働省が認定をした葬祭ディレクター技能審査があり、1級、2級とクラスがあり、合格者は一定の知識と技術をもって対応できるといった認定がされます。
認定を受けた葬祭ディレクターの存在は、葬儀社を選ぶ場合の一つの目安としてもよいでしょう。
Q3. 家族葬とは、どんなお葬式ですか?
A.
一般的には、ご予算を抑えたお葬式と考えられる方もいらっしゃるようですが、広く訃報をしないお葬式といってよいでしょう。
少人数のお葬式で、あらかじめご人数を確定するようなお葬式になりますので、結果として一昔前のお葬式よりも、価格的に抑えられ、追加のないご予算を想定できるお葬式といえます。
明確な定義はありませんが、ご家族ご親戚を中心として、ごく親しいご友人知人までを含めて、お顔ぶれを限定してお誘いする葬儀といえます。
Q4. 危篤になったときどうすればいいですか?
A.
医師から病人が危篤状態にあることを告げられたら、知らせるべき人に至急連絡をとります。近親者、親しい友人や知人、本人が会いたがっていると思われる人に知らせます。
Q5. 死亡の連絡はどこにすればいいですか?
A.
死亡が確認されたら、すぐに駆けつけて欲しい人に連絡をします。親戚の中では、一般的に2親等くらいまでに連絡するようです。
仕事関係の人には通夜や葬儀の日程が決まってから連絡します。
連絡先は電話が一般的です。緊急時なので、目上の方でも電話連絡で構いません。
朝や深夜でも一言お詫びをし、速やかに用件を述べましょう。
Q6. 危篤になったときどうすればいいですか?
A.
医師から病人が危篤状態にあることを告げられたら、知らせるべき人に至急連絡をとります。 近親者、親しい友人や知人、本人が会いたがっていると思われる人に知らせます。
Q7. 葬儀費用について教えてください。
A.
葬儀時にかかる費用は、葬儀の内容、会葬者の人数等によっても変わってきます。
お葬式はひとつとして同じものはありません。それはお一人、お一人の人生が違うのと同じですので、見積もりも1件、1件異なります。葬儀の内容、料金等については、納得がいくまで業者と話し合いの上決定しましょう。
Q8. 葬儀後にすることはなんですか?
A.
葬儀社からの請求書は、葬儀後数日して届くことが一般的です。
見積書と請求明細書を照らし合わせ、内容をしっかりチェックすることが大切です。
ご不明な点は、お支払いをされる前に必ず業者に確認して疑問点をなくしましょう。
また、社員証や身分証等があれば返却し、故人の私物を整理して持ち帰ります。
その他、ご本人名義の年金、各種保険等については、該当機関へ届出が必要になります。
手続きに必要なものを確認して、書類や印鑑等を準備します。
Q9. 危篤の知らせを受けたらどうすればいいですか?
A.
危篤の知らせを受けるのは、親族や特に親しい友人に限られます。
普段着のままで構いませんので、どこに行けばいいのかを確認し、一刻も早く駆けつけるようにしましょう。
Q10. 喪主としての挨拶はどのようなことを言えばよいのでしょうか?
A.
深い哀しみの中にあっても、会葬者へのお礼の気持ちを述べることが大切です。遺族代表の挨拶は、喪主かその代理の親族がします。聞いている会葬者も、遺族が哀しみをこらえて挨拶を述べることは辛いだろうと察していますから、簡単なもので十分です。長い時間お話をするよりも、手短に簡潔に述べた方が良いでしょう。
(例文)
遺族を代表し、一言ご挨拶を申し上げます。
本日は、ご多忙のところ、遠路ご会葬いただき、厚く御礼を申し上げます。
生前、故人に寄せられた皆様のご厚情に対し、心より御礼申し上げます。
私どもは、未熟ではありますが、故人の教えを守り、精進していく所存です。
皆様方には、故人と同様お付き合いいただき、ご指導いただけますことを
お願い申し上げます。
本日はありがとうございました。
※ 上記はあくまで例文です。実際は故人との思い出等を織り交ぜながら話すことにより、会葬者には印象深いお葬式になることでしょう。
Q11. お経や戒名に対するお布施はどのようにお渡ししたらよいでしょうか?
A.
封筒に入れ、「御布施」と表書きし、お渡しします。お経と戒名のお布施は別々の場合もありますし、一緒に含めてお渡しする場合もあります。金額については、お寺との付き合いの度合いや寺院や宗派の格等によっても異なります。
率直に住職にお尋ねしても失礼にはあたりませんので、尋ねてみましょう。「志でけっこうです」と言われた場合には、習わしを知っている方に教えていただくか、葬儀社でも大体の目安はお答えできると思います。
交通費が必要と思われる場合は「御車料」を、食事を出さない場合は「御膳料」を、相当する金額を別途に包むとよいでしょう。
Q12. 不祝儀袋の「御霊前」と「御仏前」はどう違うのですか?
A.
宗派や地域によって違いもありますが、一般的には、故人が亡くなった日から四十九日以降には「御仏前」、それより前には「御霊前」となります。ですから、通夜、葬儀、告別式に持参する香典の表書きは「御霊前」、四十九日の忌明け以降は、「御仏前」になります。